グンブロ広告
ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月
 お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。
お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。
記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2014年12月30日
坂東33観音巡り第17番札所出流山満願寺を参詣
この日坂東33観音巡り第18番札所中禅寺立木観音を後にして、日光清滝インターから徳次郎インターを下りて、19番札所宇都宮大谷寺に行ったが年末休みで参詣出来ず誠に残念だったが続いて17番札所出流山満願寺を目指しました。


大谷寺には残念ながら参詣出来なかったが寺前の売店の方から店の裏に採石場跡に彫った観音様が有りますとお聞きして観賞、手を合わせて満願寺に向かいました。
満願寺に着く前、間違って林道に入って終ったが、杉の木が多く倒れて居て雪の為の倒木と見たが被害の大きさには驚いた。幸い人が居て少し通り過ぎたと教えられ引き返し無事第17番札所満願寺に到着できました。
第17番札所満願寺は真言宗知山派でご本尊は千手観世音菩薩、開祖は勝道上人、創立は天平神衛元年「765」この寺は子授け安産の観音として多くの参詣者が居るとの事でした。







この寺には多くの石神仏像が建立祀られて居ました。満願寺の参詣を済ませ予約して置いた宇都宮の宿に向かいましたが、暗く成らない内に宿へと思って居ましたが市内が混んで暗く成って終いました。この日の走行キロ数は366キロを記録しました。


大谷寺には残念ながら参詣出来なかったが寺前の売店の方から店の裏に採石場跡に彫った観音様が有りますとお聞きして観賞、手を合わせて満願寺に向かいました。
満願寺に着く前、間違って林道に入って終ったが、杉の木が多く倒れて居て雪の為の倒木と見たが被害の大きさには驚いた。幸い人が居て少し通り過ぎたと教えられ引き返し無事第17番札所満願寺に到着できました。
第17番札所満願寺は真言宗知山派でご本尊は千手観世音菩薩、開祖は勝道上人、創立は天平神衛元年「765」この寺は子授け安産の観音として多くの参詣者が居るとの事でした。







この寺には多くの石神仏像が建立祀られて居ました。満願寺の参詣を済ませ予約して置いた宇都宮の宿に向かいましたが、暗く成らない内に宿へと思って居ましたが市内が混んで暗く成って終いました。この日の走行キロ数は366キロを記録しました。
2014年12月25日
坂東33観音巡り20番札所西明寺を訪ね
去る12月24日坂東33観音巡り第二十番札所西明寺を訪ねました。妻を伴いと念じて居ましたが、妻は最近足腰の調子が悪く、長距離、長時間のドライブには耐えられないし、あんたの目的の観音巡りの足を引っ張って終うから一人で廻ってと云われ、誠に残念だが一人で坂東33観音巡りをする事に決意しました
。

朝食を済ませて6時前出発,高速道を関越道、北関東道を経由、真岡で下りて一路西明寺へ。カーナビの案内で直行出来るのだから本当に有り難い時代だ。8時に現着。未だ早いと思ったが住職さん直々にストーブで
火を炊き、お茶を進めて呉れ恐縮した。120段の階段を上り本堂に着いた。住職さんの説明に従い本堂を参詣し、誰もおらず、撮影禁止の張り紙も無かったので仏様を写真に収めましたのでアップします。







多くの仏様にぴんぴんころりを祈願して、暫く茅葺工事もして居り、茅葺の建物と三重の塔のバランス、大きな槇の木、暫く境内を堪能して西明寺を後にしました。

。

朝食を済ませて6時前出発,高速道を関越道、北関東道を経由、真岡で下りて一路西明寺へ。カーナビの案内で直行出来るのだから本当に有り難い時代だ。8時に現着。未だ早いと思ったが住職さん直々にストーブで
火を炊き、お茶を進めて呉れ恐縮した。120段の階段を上り本堂に着いた。住職さんの説明に従い本堂を参詣し、誰もおらず、撮影禁止の張り紙も無かったので仏様を写真に収めましたのでアップします。







多くの仏様にぴんぴんころりを祈願して、暫く茅葺工事もして居り、茅葺の建物と三重の塔のバランス、大きな槇の木、暫く境内を堪能して西明寺を後にしました。

2014年12月23日
高崎市箕郷町柏木沢「本田」を散策して
先日高崎市箕郷町柏木沢本田地域を散策しました。
先ず赤城若御子神社を参詣しました。此の神社には二つの名前が有り柏木沢の総鎮守神社との事だが、赤城若御子神社と呼び、神社では鳥居に覚満神社と掲げられており、社前には元禄8年「1695年」天保9年「1838年」二対の石灯篭と狛犬が並び重厚感を誇って居ました。神社の周囲には多くの石神仏が建立祀られて居ました。
富士山型の自然石も祀られて居り、浅間大神、秋葉大神,、天満宮、金比羅大神、他にも九基の石宮も祀られて歴史の重みを感じさせますし、神社西の道を地元の人は義経街道と呼んで居て、義経が奥州下りの際に当社に参拝したと伝えられ、義経街道と関わりを示す古文書を村の旧家で家宝として残されて居ると云う事です。





続いて小高い庚申塚を訪ねました。手前に蚕影碑が祀られて居ました。碑文によると明治20年5月23日一天にわかにかき曇り、耳をつんざく雷鳴と共に大粒の雹が押し寄せる如くに降り注ぎ、たちまち1尺以上も積もった。雹の過ぎた後麦、桑、野菜類等地上から一切の緑が無く成った。ちょうど蚕は三眠なのに飼う桑がない。致し方なく養蚕家相謀って丘に穴を掘り、蚕児を涙ながらに埋めた。上に蚕影山大神の石宮を祀り、蚕霊を慰めたと記されて居ました。又同時に百庚申も建てこの惨状を後世に伝えるためにこの丘には。、猿田彦大神、青面金剛塔も明治30年と記されて有り、双体と文字塔の道祖神も祀られて居ました。
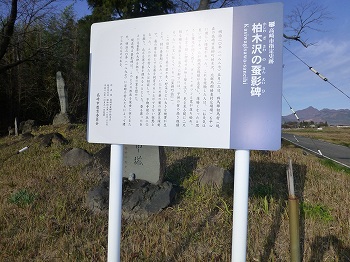



蚕影碑の少し西には八幡宮が有って参詣しました。此の宮は本田、新屋敷の鎮守様との事で、本殿の裏には
愛宕、秋葉大権現、衣笠大臣、石尊大神、天満宮、金比羅宮の石神が立ち並び又大黒天像も祀られて居ました。
八幡宮の道南には光明真言供養塔、千日惣回向塔,、女人供養の如意輪観音像等も並んで建立祀られて居ました。




更に西に群馬用水に沿って進んで新屋敷の総庚申と呼ばれる木の宮に着きました。宮には狐様が沢山供えて有るが実は十二様との事。此処でも坂東、西国、秩父、百番供養塔「明和3年「1766年」が建立祀られて居ました。私は車で坂東33観音巡りを初願して来年何とか廻り切りたいと現在考えて居るが、その昔良く百番巡礼が出来たものだとつくずく思う次第です。
又写真の様に道端には百基も有るかと思う庚申文字塔、此れは広い敷地に祀られて有ったのを一カ所に祀ったのだと云う事です。また二匹の向き合ったさるの石宮も庚申で「元禄5年「1692年」の建立







又、この12様にまつわる実話だそうですが、明治初年に本田下に「カントウベエ」と云う修験者がいて其の頃暴れ山犬が居て、里に来ては馬を襲った。たまりかねた彼は槍を引っ提げて狼を追い、この12様の辺りで狼を差し止めた。形相物凄く狼は槍に乗って肩にまでかみついたが、ひるまず顎に手をかけて口をひっさき12様の側に埋めて帰った。ところがその後毎晩狼のけんぞくなのだろうかれの屋敷に来て吠えまわった。そこで埋めた山犬を掘り起して壺におさめて屋敷内に葬った処吠えなくなった。この槍は保渡田の塚越清家に保存されたと云う。
この日柏木沢本田から新屋敷の総庚申12様迄直線では六、七百メートル位と思うが、前に取材アップした不動寺、桜薬師もこの中に有って、この地域の石佛、石神の数の多さには驚かされる。如何にこの地域の信仰心の厚さ、深さを強く感じとれた
建立当時の先人に思いを馳せ、石神仏に向かい合って居ると時間の経過して居るのに我に帰り驚く事も度々有る。
こうして石神仏を写真に納め、パソコンに入力、アップする写真を選び、コメントを考えブログの下書きで打ち込んで居ると時間の経過が早く、気が着けば二三時間も経過して居て驚く事が多く、此れだけ夢中で一日が短く感じられる趣味が持て、パソコンを習得出来た事で幸福感にしたれて居る事が本当に嬉しい。
参考文献斉藤勲先生のみさと散策
先ず赤城若御子神社を参詣しました。此の神社には二つの名前が有り柏木沢の総鎮守神社との事だが、赤城若御子神社と呼び、神社では鳥居に覚満神社と掲げられており、社前には元禄8年「1695年」天保9年「1838年」二対の石灯篭と狛犬が並び重厚感を誇って居ました。神社の周囲には多くの石神仏が建立祀られて居ました。
富士山型の自然石も祀られて居り、浅間大神、秋葉大神,、天満宮、金比羅大神、他にも九基の石宮も祀られて歴史の重みを感じさせますし、神社西の道を地元の人は義経街道と呼んで居て、義経が奥州下りの際に当社に参拝したと伝えられ、義経街道と関わりを示す古文書を村の旧家で家宝として残されて居ると云う事です。





続いて小高い庚申塚を訪ねました。手前に蚕影碑が祀られて居ました。碑文によると明治20年5月23日一天にわかにかき曇り、耳をつんざく雷鳴と共に大粒の雹が押し寄せる如くに降り注ぎ、たちまち1尺以上も積もった。雹の過ぎた後麦、桑、野菜類等地上から一切の緑が無く成った。ちょうど蚕は三眠なのに飼う桑がない。致し方なく養蚕家相謀って丘に穴を掘り、蚕児を涙ながらに埋めた。上に蚕影山大神の石宮を祀り、蚕霊を慰めたと記されて居ました。又同時に百庚申も建てこの惨状を後世に伝えるためにこの丘には。、猿田彦大神、青面金剛塔も明治30年と記されて有り、双体と文字塔の道祖神も祀られて居ました。
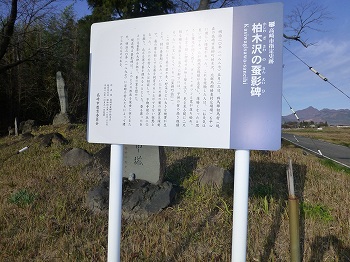



蚕影碑の少し西には八幡宮が有って参詣しました。此の宮は本田、新屋敷の鎮守様との事で、本殿の裏には
愛宕、秋葉大権現、衣笠大臣、石尊大神、天満宮、金比羅宮の石神が立ち並び又大黒天像も祀られて居ました。
八幡宮の道南には光明真言供養塔、千日惣回向塔,、女人供養の如意輪観音像等も並んで建立祀られて居ました。




更に西に群馬用水に沿って進んで新屋敷の総庚申と呼ばれる木の宮に着きました。宮には狐様が沢山供えて有るが実は十二様との事。此処でも坂東、西国、秩父、百番供養塔「明和3年「1766年」が建立祀られて居ました。私は車で坂東33観音巡りを初願して来年何とか廻り切りたいと現在考えて居るが、その昔良く百番巡礼が出来たものだとつくずく思う次第です。
又写真の様に道端には百基も有るかと思う庚申文字塔、此れは広い敷地に祀られて有ったのを一カ所に祀ったのだと云う事です。また二匹の向き合ったさるの石宮も庚申で「元禄5年「1692年」の建立







又、この12様にまつわる実話だそうですが、明治初年に本田下に「カントウベエ」と云う修験者がいて其の頃暴れ山犬が居て、里に来ては馬を襲った。たまりかねた彼は槍を引っ提げて狼を追い、この12様の辺りで狼を差し止めた。形相物凄く狼は槍に乗って肩にまでかみついたが、ひるまず顎に手をかけて口をひっさき12様の側に埋めて帰った。ところがその後毎晩狼のけんぞくなのだろうかれの屋敷に来て吠えまわった。そこで埋めた山犬を掘り起して壺におさめて屋敷内に葬った処吠えなくなった。この槍は保渡田の塚越清家に保存されたと云う。
この日柏木沢本田から新屋敷の総庚申12様迄直線では六、七百メートル位と思うが、前に取材アップした不動寺、桜薬師もこの中に有って、この地域の石佛、石神の数の多さには驚かされる。如何にこの地域の信仰心の厚さ、深さを強く感じとれた
建立当時の先人に思いを馳せ、石神仏に向かい合って居ると時間の経過して居るのに我に帰り驚く事も度々有る。
こうして石神仏を写真に納め、パソコンに入力、アップする写真を選び、コメントを考えブログの下書きで打ち込んで居ると時間の経過が早く、気が着けば二三時間も経過して居て驚く事が多く、此れだけ夢中で一日が短く感じられる趣味が持て、パソコンを習得出来た事で幸福感にしたれて居る事が本当に嬉しい。
参考文献斉藤勲先生のみさと散策
2014年12月11日
高崎市箕郷町生原中新田地区を散策して
先日高崎市箕郷町生原中新田地域を散策しました。
中新田一番南に善竜寺が有りますが前に取材アップして居り、通り過ぎて南から中新田に入りましたが、部落の入口を示すように道祖神が並んで建立されて居ました。
が、手前が文字塔、並んで建立されて居たのは明らかに双体道祖神と思われるが写真の通り破壊されて居ました。誰が何で破壊したのか腹が立ちました。
調べて見たら二神合唱型で宝暦12年「1762年」の建立、文字塔は明和2年「1765年」に建立されて居ました。


少し北には飯野家の墓所が有り参詣しました。墓所手前には多くの石仏が建立祀られて居ました。


「
飯野家の墓所には如意輪観音も祀られて居り、平成18年行年百歳で亡くなられた戦中陸軍少佐で勲5等を受賞した飯野光蔵氏も眠って居て偉い人が居た事も知りました。


飯野家の墓所前には穴薬師が祀られて居り、上は竹藪に成って居り古墳との事、中には石の薬師様が祀られて傍に回国僧が残していったという剥げた木のお地蔵様が置かれて居ました。



又北に進むと中新田四辻にホウソウ除けの神、疱瘡軽安守護神を祀った碑「安政5年「1859年」が立って居て、昔の人達にはホウソウは脅威だったのでしょう

北に進み県道の信号が見える処に、山の神と云われ多くの石神仏が建立祀られて居り参詣しました
天満大自在天神,水雨天吹風天天神舟入「万延2年「1861年」穂高大権現八海山大頭羅神王三笠山刀利夫「安政2年「1795年」阿留魔邪天狗御嶽山座主摩利支尊天「安政2年「1795年」等多くの山神が祀られて居り。山神信仰の講中で賑わった往時を偲びつつ、暫く参詣してきました





この日車では目に着かない物も眼に留まり赤い実が良くついた南天、たわわに実り黄色に色着いた柚子を写真に収めて来ました。



参考文献箕郷町石造文化財
中新田一番南に善竜寺が有りますが前に取材アップして居り、通り過ぎて南から中新田に入りましたが、部落の入口を示すように道祖神が並んで建立されて居ました。
が、手前が文字塔、並んで建立されて居たのは明らかに双体道祖神と思われるが写真の通り破壊されて居ました。誰が何で破壊したのか腹が立ちました。
調べて見たら二神合唱型で宝暦12年「1762年」の建立、文字塔は明和2年「1765年」に建立されて居ました。
少し北には飯野家の墓所が有り参詣しました。墓所手前には多くの石仏が建立祀られて居ました。
「
飯野家の墓所には如意輪観音も祀られて居り、平成18年行年百歳で亡くなられた戦中陸軍少佐で勲5等を受賞した飯野光蔵氏も眠って居て偉い人が居た事も知りました。
飯野家の墓所前には穴薬師が祀られて居り、上は竹藪に成って居り古墳との事、中には石の薬師様が祀られて傍に回国僧が残していったという剥げた木のお地蔵様が置かれて居ました。
又北に進むと中新田四辻にホウソウ除けの神、疱瘡軽安守護神を祀った碑「安政5年「1859年」が立って居て、昔の人達にはホウソウは脅威だったのでしょう
北に進み県道の信号が見える処に、山の神と云われ多くの石神仏が建立祀られて居り参詣しました
天満大自在天神,水雨天吹風天天神舟入「万延2年「1861年」穂高大権現八海山大頭羅神王三笠山刀利夫「安政2年「1795年」阿留魔邪天狗御嶽山座主摩利支尊天「安政2年「1795年」等多くの山神が祀られて居り。山神信仰の講中で賑わった往時を偲びつつ、暫く参詣してきました
この日車では目に着かない物も眼に留まり赤い実が良くついた南天、たわわに実り黄色に色着いた柚子を写真に収めて来ました。
参考文献箕郷町石造文化財
2014年10月23日
箕郷町の石造文化財に魅せられて
箕郷町の石造文化財に魅せられて通い始めてもう半年以上に成るが中々石造物
はこの辺と見当をつけて出向いても見つからない事が多く、同年代の箕郷町柏木沢に住む従兄に嘆いた処、調べて案内をして呉れると約束して呉れました。
そして去る10月17日第一回目の案内をして呉れました。
先ず柏木沢新田、本田、今宮、生原の石造文化財のある場所を半日かけて案内して呉れました。


出掛けても何時も人影さえ見られずお伺いする事が出来ずに居ましたが此れで何日もかけて案内されたこの地域の石造物に会いに行けます。
従兄は解らない事は友人に聞いて箕郷町全体の石造物を字別に調べては何回かに分けて案内して呉れると約束して呉れ本当に有り難い事です。
早速案内して戴いた一部の石造文化財に本日会いに行って来ました。
柏木沢本田の十字路の道標、八幡宮入口を示す大きな御神燈と並んで建立されて居ました。高崎、前橋、、安中、榛名、渋川迄の里程も彫って有り,大正6年青年会と彫られて有りました。
続いて元柏木沢本田上で先の合併の時、住民投票の結果榛東村にへの合併が一票差で勝って、現在榛東村広馬場の柏木宿を訪ねました。
こんな近くに宿と呼ばれた地域が有ったとは知りませんでした。柏木宿の立て看板が建てられており案内が記されて有りました。


大きな庚申塔が建立されて居て願主は村中と彫られ、多くの庚申文字塔は個人で建立して有りました。
一番新しい庚申塔は昭和55年の庚申年の建立でした。大きい庚申塔には元総理大臣福田赳夫先生お書きの字で彫られて有りました。矢張り昭和55年庚申年の建立です、庚申主尊の青面金剛像も祀られて居りました。
寺入口には大きな馬頭観音の文字塔が建立されて居り銘には元治紀元甲子年当山現住良海代と彫られて居ました。

右庚申塔の文字は元総理大臣福田赳夫先生の文字でした。
4列に庚申文字塔が建立されて居り、昭和55年庚申年の建立された庚申文字塔も祀られて有りました。

宿に有った無住寺本堂近所の人が掃除して居ました
門前にお地蔵様、馬頭観音が祀られて居ました又22夜講の如意輪観音も建立されて居り女人講が盛んだった事も偲ばれました。


柏木宿の家々にはご覧の様に屋号書いた看板が立って居ました。
はこの辺と見当をつけて出向いても見つからない事が多く、同年代の箕郷町柏木沢に住む従兄に嘆いた処、調べて案内をして呉れると約束して呉れました。
そして去る10月17日第一回目の案内をして呉れました。
先ず柏木沢新田、本田、今宮、生原の石造文化財のある場所を半日かけて案内して呉れました。


出掛けても何時も人影さえ見られずお伺いする事が出来ずに居ましたが此れで何日もかけて案内されたこの地域の石造物に会いに行けます。
従兄は解らない事は友人に聞いて箕郷町全体の石造物を字別に調べては何回かに分けて案内して呉れると約束して呉れ本当に有り難い事です。
早速案内して戴いた一部の石造文化財に本日会いに行って来ました。
柏木沢本田の十字路の道標、八幡宮入口を示す大きな御神燈と並んで建立されて居ました。高崎、前橋、、安中、榛名、渋川迄の里程も彫って有り,大正6年青年会と彫られて有りました。
続いて元柏木沢本田上で先の合併の時、住民投票の結果榛東村にへの合併が一票差で勝って、現在榛東村広馬場の柏木宿を訪ねました。
こんな近くに宿と呼ばれた地域が有ったとは知りませんでした。柏木宿の立て看板が建てられており案内が記されて有りました。


大きな庚申塔が建立されて居て願主は村中と彫られ、多くの庚申文字塔は個人で建立して有りました。
一番新しい庚申塔は昭和55年の庚申年の建立でした。大きい庚申塔には元総理大臣福田赳夫先生お書きの字で彫られて有りました。矢張り昭和55年庚申年の建立です、庚申主尊の青面金剛像も祀られて居りました。
寺入口には大きな馬頭観音の文字塔が建立されて居り銘には元治紀元甲子年当山現住良海代と彫られて居ました。

右庚申塔の文字は元総理大臣福田赳夫先生の文字でした。

4列に庚申文字塔が建立されて居り、昭和55年庚申年の建立された庚申文字塔も祀られて有りました。

宿に有った無住寺本堂近所の人が掃除して居ました

門前にお地蔵様、馬頭観音が祀られて居ました又22夜講の如意輪観音も建立されて居り女人講が盛んだった事も偲ばれました。


柏木宿の家々にはご覧の様に屋号書いた看板が立って居ました。
2014年09月24日
高崎市箕郷町松原地域を散策して
箕郷町松原地区には前回、八幡神社を取材アップした事も有りました。その中で頭に角を生やし、ばちを手に雲に乗った雷神像、箕郷町では唯一、県内でも珍しい雷神像をアップしてますが、今回はゆっくり村人との対話を望み、広い空地に車を置いて散策しました。
幸い高齢で家庭菜園の作業して居た方に、松原地域の色々の話を聞くことが出来ました。
そして、山岳信仰の御嶽講の祭殿が祀られて居る事、百庚申、くめどの薬師、墓地等の場所も聴くことが出来て、全部写真に収める事が出来、大変助かりました。車で走って居るだけでは、石造物が有っても見逃してしまいますが、次からも目的の地域に行ったら必ず車は止めて散策乍ら石造物に巡り合いたいと思いました。

前回もアップした雷神像、群馬は雷の多い県、当地では今年は比較的雷様の被害は少なかったと思います。

お聞きした御嶽講の祭殿、立派な祭殿でした。例大祭には多くの人が白装束鉢巻き姿で集合,関東中に御嶽講に入って居る人が居て遠方からも来るとの説明でした。

地元の人が小榛名山と呼ぶ小高い丘が有り、上って見るとお宮が建立されて居り榛名山を祀って居ました。


真ん中に大きな庚申供養塔を祀り、両側に多くの小さな庚申文字塔が祀られて居り、此れを松原の百庚申と地元では読んで居ます。


続いてくめどの墓地を訪ねました。立派な宝篋印塔、千手観音像「1788年「天明8年」が祀られて居ました。
参考文献箕郷町の石造文化財
幸い高齢で家庭菜園の作業して居た方に、松原地域の色々の話を聞くことが出来ました。
そして、山岳信仰の御嶽講の祭殿が祀られて居る事、百庚申、くめどの薬師、墓地等の場所も聴くことが出来て、全部写真に収める事が出来、大変助かりました。車で走って居るだけでは、石造物が有っても見逃してしまいますが、次からも目的の地域に行ったら必ず車は止めて散策乍ら石造物に巡り合いたいと思いました。

前回もアップした雷神像、群馬は雷の多い県、当地では今年は比較的雷様の被害は少なかったと思います。

お聞きした御嶽講の祭殿、立派な祭殿でした。例大祭には多くの人が白装束鉢巻き姿で集合,関東中に御嶽講に入って居る人が居て遠方からも来るとの説明でした。

地元の人が小榛名山と呼ぶ小高い丘が有り、上って見るとお宮が建立されて居り榛名山を祀って居ました。


真ん中に大きな庚申供養塔を祀り、両側に多くの小さな庚申文字塔が祀られて居り、此れを松原の百庚申と地元では読んで居ます。


続いてくめどの墓地を訪ねました。立派な宝篋印塔、千手観音像「1788年「天明8年」が祀られて居ました。
参考文献箕郷町の石造文化財
2014年09月22日
高崎市箕郷町松之沢地域を散策して其の二
松沢寺跡を後にして村外れに有ると云う神社を目指しました。途中バス停が有り広く成って居り、車を止めて見ると、石造物が有りました。丁度村人が居て、松之沢の事について種々お話を聞くことが出来ました。此処には榛東村に通ずる隧道、水の取り入れ口が有り、昔水利権で争いも有ったとの事です。石造物、弁財天像が祀られて居ました。『1763年「宝暦13年」の建立、弁財天さんのお顔は誠に柔和なお顔で可成りの名工の作だと思われました。

隧道、水の取り入れ口


村外れの神社は若御子神社「わかみこじんじゃ」と云い、三抱え以上あると思われる杉の巨木に覆われた静な佇まい、万行山大権現、石鳥居の額にも万行山と書かれて、朝夕に仰ぐ榛名の山がこの社の祭神だと村人が教えて呉れました。又、此の神社は榛名神社よりも早く祀られ建立されたとの事です。

戦後には神社、仏閣の大木は殆ど伐採されたのにこの若神子神社の杉の巨木良く残して置いたと思いました。

神社裏には多くの石造物が夏草に覆われ祀られて居ました

大黒天[1864年「元治元年」の建立

黒髪神山神社建立銘なし

路傍から移されここに祀られたと思われる。向き合った二神合唱型1753年「宝暦3年」建立と[1825年「文政8年」建立の文字塔道祖神が祀られて有りました。
参考文献箕郷町の石造文化財

隧道、水の取り入れ口


村外れの神社は若御子神社「わかみこじんじゃ」と云い、三抱え以上あると思われる杉の巨木に覆われた静な佇まい、万行山大権現、石鳥居の額にも万行山と書かれて、朝夕に仰ぐ榛名の山がこの社の祭神だと村人が教えて呉れました。又、此の神社は榛名神社よりも早く祀られ建立されたとの事です。
戦後には神社、仏閣の大木は殆ど伐採されたのにこの若神子神社の杉の巨木良く残して置いたと思いました。

神社裏には多くの石造物が夏草に覆われ祀られて居ました

大黒天[1864年「元治元年」の建立

黒髪神山神社建立銘なし

路傍から移されここに祀られたと思われる。向き合った二神合唱型1753年「宝暦3年」建立と[1825年「文政8年」建立の文字塔道祖神が祀られて有りました。
参考文献箕郷町の石造文化財
2014年09月20日
高崎市箕郷町松之沢地域を散策して
高崎市箕郷町松之沢には前に百観音を取材アップして居ります。松之沢には百観音の他にも鎮守様、松沢寺「しょうたくじ」跡にも多くの石造文化財が有るとお聞きして9月19日午後行き、ゆったり散策乍ら写真に収めて来ました。
昔、箕郷町松之沢部落は随分山奥の山村だなと思って居りましたが、現在は道も良く成り、榛名湖への近道で年間何回も通りますし、広大な芝桜公園も有り、毎年見に行って居りますが部落を散策した事は有りませんでした。今回最初に松沢寺跡を訪ねました

松沢寺跡はこんもりと茂った木の下に多くの石造物が祀られて居り一番に青面金剛塔が目に着きました。「1860年「万延元年」の建立

庚申建立年無し
」
「建立年無し」

馬頭尊像建立年無し」
地蔵尊像建立年無し」


二十二夜様の主尊如意輪観音像、、供養塔も建立されて居て、村人の信仰の深さを覗い知りました。次に村外れに有ると云う神社に向かいましたが、松沢寺跡近くに多くの彼岸花が咲いて居り写真に収めて来ました、こんなに密生している彼岸花は、最近田の畔には見られなくなりました。


参考文献 箕郷町の石造文化財
昔、箕郷町松之沢部落は随分山奥の山村だなと思って居りましたが、現在は道も良く成り、榛名湖への近道で年間何回も通りますし、広大な芝桜公園も有り、毎年見に行って居りますが部落を散策した事は有りませんでした。今回最初に松沢寺跡を訪ねました

松沢寺跡はこんもりと茂った木の下に多くの石造物が祀られて居り一番に青面金剛塔が目に着きました。「1860年「万延元年」の建立

庚申建立年無し
」

「建立年無し」

馬頭尊像建立年無し」

地蔵尊像建立年無し」


二十二夜様の主尊如意輪観音像、、供養塔も建立されて居て、村人の信仰の深さを覗い知りました。次に村外れに有ると云う神社に向かいましたが、松沢寺跡近くに多くの彼岸花が咲いて居り写真に収めて来ました、こんなに密生している彼岸花は、最近田の畔には見られなくなりました。


参考文献 箕郷町の石造文化財
2014年09月07日
箕郷町西明屋妙福寺を訪ねて
高崎市箕郷町西明屋妙福寺を訪ねました。此のお寺は鬼子母神で有名で青年時代何回も行った事が有るお寺です。当時は毎年行われる例大祭の日には露店が何十軒も並び大変混みあったのを思い出しました。現在でも例大祭の日は参詣客が多いいと住職さんの説明でした。


先に結界石について説明アップしましたが、今回は題目塔について説明アップします。下、2枚の写真は、二基の題目塔です。
題目とは経典の題名をさす。日蓮宗開祖の日蓮は釈迦の教えの神髄は法華経に有ると説き、その題名で有る妙法蓮華経に南無[仏の教えに従う意」を冠して「南無妙法蓮華経」の題目を唱える事を創めた。信徒は太鼓を叩き、題目を唱えて、現生の利益と後世の善処を祈った。題目塔は一結の衆、後には講中により建てられた供養塔である。塔の題目の文字の一部が長く伸びて書かれる。このヒゲは光明をはなち,威光を表すと伝えられて居る。


上、二枚の写真で『南無妙法蓮華経」の字の一部にひげが伸びているのがよく解ると思います。確認下さい。

境内に入ると馬頭尊像「1764年「宝暦14年」も建立されて居ました。先日アップした結界石が生原の善竜寺にも有るとお聞きして帰りに寄って見ました。善竜寺は最近取材アップした時には気が着きませんでしたが、山門前に結界石が建立されて居り驚きました。

参考文献箕郷町石造文化財


先に結界石について説明アップしましたが、今回は題目塔について説明アップします。下、2枚の写真は、二基の題目塔です。
題目とは経典の題名をさす。日蓮宗開祖の日蓮は釈迦の教えの神髄は法華経に有ると説き、その題名で有る妙法蓮華経に南無[仏の教えに従う意」を冠して「南無妙法蓮華経」の題目を唱える事を創めた。信徒は太鼓を叩き、題目を唱えて、現生の利益と後世の善処を祈った。題目塔は一結の衆、後には講中により建てられた供養塔である。塔の題目の文字の一部が長く伸びて書かれる。このヒゲは光明をはなち,威光を表すと伝えられて居る。


上、二枚の写真で『南無妙法蓮華経」の字の一部にひげが伸びているのがよく解ると思います。確認下さい。

境内に入ると馬頭尊像「1764年「宝暦14年」も建立されて居ました。先日アップした結界石が生原の善竜寺にも有るとお聞きして帰りに寄って見ました。善竜寺は最近取材アップした時には気が着きませんでしたが、山門前に結界石が建立されて居り驚きました。

参考文献箕郷町石造文化財
2014年09月05日
箕郷町白川白川神社を参詣して
高崎市箕郷町白川白川神社を参詣しました。神社入口に自然石に深く彫った字も鮮やかな庚申塔が建立祀られて居ました
境内に入ると本堂、西脇には多くの石宮が祀られ、お稲荷様を祀ってありました。
神社東には秋葉大神、猿田彦大神、道祖神文字塔、八海山神社等多くの石造神仏が祀られて居ました。

彫り深く字の鮮明な庚申塔「1800年「寛政2年」の建立

神社本堂

多くの石宮が祀られて居り、稲荷様が祀られて居ました

道祖神文字塔1788年寛政10年から1851年嘉永5年迄に建立された道祖神文字塔7基が祀られて居ました。
左秋葉大神「1920年「大正9年」の建立右猿田彦大1920年「大正9年」の建立

御嶽座主大権現「1862年「文久2年」の建立、神社の境内も広く、此の地域住民の信仰の深さが覗い知れて歴史の重みを感じさせて呉れた白川神社でした。
境内に入ると本堂、西脇には多くの石宮が祀られ、お稲荷様を祀ってありました。
神社東には秋葉大神、猿田彦大神、道祖神文字塔、八海山神社等多くの石造神仏が祀られて居ました。

彫り深く字の鮮明な庚申塔「1800年「寛政2年」の建立

神社本堂

多くの石宮が祀られて居り、稲荷様が祀られて居ました

道祖神文字塔1788年寛政10年から1851年嘉永5年迄に建立された道祖神文字塔7基が祀られて居ました。

左秋葉大神「1920年「大正9年」の建立右猿田彦大1920年「大正9年」の建立

御嶽座主大権現「1862年「文久2年」の建立、神社の境内も広く、此の地域住民の信仰の深さが覗い知れて歴史の重みを感じさせて呉れた白川神社でした。
2014年09月04日
箕郷町原新田龍昌寺を訪ねて
高崎市箕郷町生原原新田龍昌寺を訪ねました。参道入り口にお地蔵様、子育観音像、青面金剛像、西国供養塔と並んで建立祀られて居ました。参道わきに川浦家の墓地が有り、暫くお邪魔して石造仏に向かい合い、拝んで来ました。
墓地内には六地蔵灯篭、如意輪観音像、馬頭観世音等建立祀られて居ました。


地蔵尊立像「建立年無し」

子育観音像「建立年無し」

青面金剛像

観世音菩薩

多くの墓地を見させて戴いて居りますが、六地蔵灯篭は珍しいです。


私は石神仏に興味を抱き、勉強して寫眞に収めアップして来ましたが、今回初めて結界石を知りました。
結界石とは寺院の門前に建てられて居る、「不許葷酒「くんしゅ」入山門」等の銘文の有る石塔の事。
結界とは辞書で調べたら、仏教で僧の修業の為に衣食住を制限する事,禁制と有り、又石仏入門書によると語句の葷はニラ、ニンニク、ネギ、等の臭気の有る蔬菜類とトウガラシ等辛味の有る刺激性のものをさしている。これは俗界人が山内にこれらのものを携えて立ち入ることは山内を不浄にし、修行の妨げとなるので禁じる意味が有ると記されて居ります。
龍昌寺では西国坂東秩父百番供養塔の側面道路側に「不許葷酒入山門」と彫られ建立されて居ました。
墓地内には六地蔵灯篭、如意輪観音像、馬頭観世音等建立祀られて居ました。


地蔵尊立像「建立年無し」

子育観音像「建立年無し」

青面金剛像

観世音菩薩

多くの墓地を見させて戴いて居りますが、六地蔵灯篭は珍しいです。


私は石神仏に興味を抱き、勉強して寫眞に収めアップして来ましたが、今回初めて結界石を知りました。
結界石とは寺院の門前に建てられて居る、「不許葷酒「くんしゅ」入山門」等の銘文の有る石塔の事。
結界とは辞書で調べたら、仏教で僧の修業の為に衣食住を制限する事,禁制と有り、又石仏入門書によると語句の葷はニラ、ニンニク、ネギ、等の臭気の有る蔬菜類とトウガラシ等辛味の有る刺激性のものをさしている。これは俗界人が山内にこれらのものを携えて立ち入ることは山内を不浄にし、修行の妨げとなるので禁じる意味が有ると記されて居ります。
龍昌寺では西国坂東秩父百番供養塔の側面道路側に「不許葷酒入山門」と彫られ建立されて居ました。
2014年09月02日
箕郷町白川滝沢寺を訪ねて
高崎市箕郷町白川滝沢寺を参詣しました。山門入口に大きな石造仁王尊像が左右に睨みをきかして建立されて居ました。私は石造仁王尊像に出会ったのは初めてでした。
仁王尊像は金剛力士像ともいわれて、右手に金剛杵、左掌を胸前に開いて、怒りの形相すごく仏敵を睨み、口を開いた阿形像を蜜迹金剛。右の肘を高く張り、金剛掌杵を腰にかまえ怒りあらわな姿で口を閉ざした吽形像を那羅延金剛という。
仁王尊像は、仏法を守る役目を持って居る。二尊は配置上左右に必要なわけで,別体ではないとされて居る。「この項日本石仏協会編石仏入門書参照」




山門入口左にはお地蔵様が祀られて居ました「1718年「享保4年」の建立

お地蔵様と並んで庚申供養塔「1740年[元文5年」建立から「1860年「万延元年」建立の青面金剛塔等5基の庚申供養塔も祀られて居ました。

本堂も立派で,池の水も清らかで多くの鯉が餌を求めて寄って来ました。

参道入り口右側には立派な経蔵も建立されて居り、梅林、田園に囲まれた誠に静かなお寺で心癒されて帰宅しました。
参考文献 箕郷町石造文化財
仁王尊像は金剛力士像ともいわれて、右手に金剛杵、左掌を胸前に開いて、怒りの形相すごく仏敵を睨み、口を開いた阿形像を蜜迹金剛。右の肘を高く張り、金剛掌杵を腰にかまえ怒りあらわな姿で口を閉ざした吽形像を那羅延金剛という。
仁王尊像は、仏法を守る役目を持って居る。二尊は配置上左右に必要なわけで,別体ではないとされて居る。「この項日本石仏協会編石仏入門書参照」




山門入口左にはお地蔵様が祀られて居ました「1718年「享保4年」の建立

お地蔵様と並んで庚申供養塔「1740年[元文5年」建立から「1860年「万延元年」建立の青面金剛塔等5基の庚申供養塔も祀られて居ました。

本堂も立派で,池の水も清らかで多くの鯉が餌を求めて寄って来ました。


参道入り口右側には立派な経蔵も建立されて居り、梅林、田園に囲まれた誠に静かなお寺で心癒されて帰宅しました。
参考文献 箕郷町石造文化財
2014年08月31日
箕郷町上芝金竜寺を訪ねて
高崎市箕郷町上芝金竜寺を訪ねました。山門をくぐりすぐ右側に庚申供養塔、青面金剛塔が祀られて居ました。

金竜寺本堂

庚申供養塔「1775年「安永5年」の建立

庚申塔「1860年「万延元年」の建立

青面金剛塔「1860年「安政7年」の建立
南無大悲観世音「1699年「元禄12年」の建立

苔に覆われた奪衣婆像が祀られて居ましたが、大閻魔像の姿は見えませんでした。「建立年無し」


多くの不動明王、文字塔、不動明王像「建立年無し」が祀られて居りましたが、近年他から移築され祀られて居ると云う事です。
参考文献箕郷町石造文化財
金竜寺本堂
庚申供養塔「1775年「安永5年」の建立
庚申塔「1860年「万延元年」の建立
青面金剛塔「1860年「安政7年」の建立
南無大悲観世音「1699年「元禄12年」の建立
苔に覆われた奪衣婆像が祀られて居ましたが、大閻魔像の姿は見えませんでした。「建立年無し」
多くの不動明王、文字塔、不動明王像「建立年無し」が祀られて居りましたが、近年他から移築され祀られて居ると云う事です。
参考文献箕郷町石造文化財
2014年08月29日
箕郷町東明屋諏訪神社を参詣して
高崎市箕郷町東明屋諏訪神社を参詣しました。諏訪神社は箕輪城址東側に隣接して居ります。
諏訪神社入口道東に秋葉大根現が建立祀られて居ました。秋葉様は火伏の神様で現在でも多くの地区で秋葉講は開かれて居る事を見聞きして居ります。神社に入ると大きな杉の木立の中に静かに祀られて居ました。




此処では本堂諏訪神社が建立されて居ましたが、書上神社、榛名神社、大山袛神社などの文字塔も建立されて居て不思議に思いまた。

二神献酬型道祖神像が建立祀られて居ましたが、おそらく路傍の道祖神を神社に移して祀られて居る様でした。「1781年天明元年」の建立。

四国、西国、秩父、坂東供養塔「文政元年「1816年」の建立。この種の供養塔は、地区や友達からお賽銭を預かり、各地に代参、帰郷後に皆で建立祀った物だと、箕輪城語り部の会長さん岡田先生の説明でした

又神社で有りながら、大日尊も建立祀られて居て、不思議に思いました。「1857年「安政4年」の建立
参考文献 箕郷町石造文化財
諏訪神社入口道東に秋葉大根現が建立祀られて居ました。秋葉様は火伏の神様で現在でも多くの地区で秋葉講は開かれて居る事を見聞きして居ります。神社に入ると大きな杉の木立の中に静かに祀られて居ました。




此処では本堂諏訪神社が建立されて居ましたが、書上神社、榛名神社、大山袛神社などの文字塔も建立されて居て不思議に思いまた。

二神献酬型道祖神像が建立祀られて居ましたが、おそらく路傍の道祖神を神社に移して祀られて居る様でした。「1781年天明元年」の建立。

四国、西国、秩父、坂東供養塔「文政元年「1816年」の建立。この種の供養塔は、地区や友達からお賽銭を預かり、各地に代参、帰郷後に皆で建立祀った物だと、箕輪城語り部の会長さん岡田先生の説明でした

又神社で有りながら、大日尊も建立祀られて居て、不思議に思いました。「1857年「安政4年」の建立
参考文献 箕郷町石造文化財
2014年08月25日
生原善竜寺を訪ねて
高崎市箕郷町生原善竜寺を訪ねました、始めに善竜寺境内前の内藤塚を訪ねました。

内藤塚は武田信玄による箕輪城攻略の後、重臣の内藤昌豊が箕輪城に入り統治した。長篠の戦いで討ち死にした昌豊と、その子昌月親子を葬ったと伝えられて二基の五輪塔が並んで建立「建立年銘無し」祀られて居ました。右側を父昌豊、左側昌月のお墓と云われて居るとの事です。又多重塔も建立されて居ました。立て看板を読むと一名開祖塚とも云うと記されて居ました。



善竜寺は曹洞宗のお寺で万行山と号して、立派なお寺で本堂前には大きな聖観音像が建立祀られて居ました。


本堂裏には32世代の住職さんのお墓や、昔のお墓が並んで祀られ
て居ました。
参考文献箕郷町石造文化財

内藤塚は武田信玄による箕輪城攻略の後、重臣の内藤昌豊が箕輪城に入り統治した。長篠の戦いで討ち死にした昌豊と、その子昌月親子を葬ったと伝えられて二基の五輪塔が並んで建立「建立年銘無し」祀られて居ました。右側を父昌豊、左側昌月のお墓と云われて居るとの事です。又多重塔も建立されて居ました。立て看板を読むと一名開祖塚とも云うと記されて居ました。



善竜寺は曹洞宗のお寺で万行山と号して、立派なお寺で本堂前には大きな聖観音像が建立祀られて居ました。


本堂裏には32世代の住職さんのお墓や、昔のお墓が並んで祀られ
て居ました。
参考文献箕郷町石造文化財
2014年08月20日
観音寺集会所石造仏群に気づいて
盆送りの翌日17日に高崎市棟高町観音寺地区集会所前の道を用事で通り、団子が沢山供えられた石像仏群が目に着き車を止めてカメラに収めて来ました。よく通る道でしたが今迄に気が付かず通って居ました。


集会所直ぐ隣の駐車場に車を止め、先ず馬頭尊の文字塔、馬頭尊像の多さに驚きました。天保年間から、可成り長い年月、馬に感謝して建立祀った物と考えられます。

明治9年「1876年」建立

建立年不詳、可成り古い年代と思われます。

文化14年「1817年」建立女人講願主の銘有り
良く見させて貰うと、女人講が盛んだった地域の様で、二十二夜塔が二基、子育観音像が一基、女人講にて建立祀って有りました

万延元年9月庚申の銘有リ【1878年」
月山、湯殿山、羽黒山の百番供養塔「万延元年庚申9月」1878年」の銘有りも建立祀られて居り山の信仰も盛んだった地域と思われました。

西国分の二十二夜供養塔の台座でも窪みが有り、伺って見ると、私と同年代の人達は子どもの頃餅草を石で叩いて遊んだ記憶が有りと話して居りましたが、此処でも台座に同じ窪みが有りました。
集会所直ぐ隣の駐車場に車を止め、先ず馬頭尊の文字塔、馬頭尊像の多さに驚きました。天保年間から、可成り長い年月、馬に感謝して建立祀った物と考えられます。

明治9年「1876年」建立

建立年不詳、可成り古い年代と思われます。

文化14年「1817年」建立女人講願主の銘有り
良く見させて貰うと、女人講が盛んだった地域の様で、二十二夜塔が二基、子育観音像が一基、女人講にて建立祀って有りました

万延元年9月庚申の銘有リ【1878年」
月山、湯殿山、羽黒山の百番供養塔「万延元年庚申9月」1878年」の銘有りも建立祀られて居り山の信仰も盛んだった地域と思われました。

西国分の二十二夜供養塔の台座でも窪みが有り、伺って見ると、私と同年代の人達は子どもの頃餅草を石で叩いて遊んだ記憶が有りと話して居りましたが、此処でも台座に同じ窪みが有りました。
2014年08月18日
箕郷町西明屋松山寺を訪ねて
。高崎市箕郷町西明屋松山寺を訪ねました。松山寺には戦争中、軍に徴収された各寺の鐘楼を尻目に、近隣では只一つ重要文化財の指定を受けて徴収を免れた鐘楼との事で箕郷町重要文化財に指定されて居ります。


先の戦争末期何処のお寺の鐘も軍に徴集され、こんな鐘まで大砲の弾にするのだと聞いて子供心にも、こんな鐘まで持って行き弾にするのか、日本は原料に乏しい国だと思った事を忘れられません。
上本堂と鐘楼。


六地蔵像の真ん中に建立祀られて居た大日如来丸彫り座像、六地蔵と共に建立年の銘は有りませんでした。

他に1798年【寛政10年」建立の大日如来丸彫り座像が祀られて居ました。


広い境内西側には青面金剛塔、庚申供養塔も建立祀られて居り、「両塔共1860年「万延元年」の建立、寺と地域との密接な関係を強く思い、寺を後にしました。何処の寺院に赴いても心癒されるものが有ります。
参考文献箕郷町の石造文化財


先の戦争末期何処のお寺の鐘も軍に徴集され、こんな鐘まで大砲の弾にするのだと聞いて子供心にも、こんな鐘まで持って行き弾にするのか、日本は原料に乏しい国だと思った事を忘れられません。
上本堂と鐘楼。


六地蔵像の真ん中に建立祀られて居た大日如来丸彫り座像、六地蔵と共に建立年の銘は有りませんでした。

他に1798年【寛政10年」建立の大日如来丸彫り座像が祀られて居ました。


広い境内西側には青面金剛塔、庚申供養塔も建立祀られて居り、「両塔共1860年「万延元年」の建立、寺と地域との密接な関係を強く思い、寺を後にしました。何処の寺院に赴いても心癒されるものが有ります。
参考文献箕郷町の石造文化財
2014年07月23日
箕郷町柏木沢今宮八幡神社を訪ねて
高崎市箕郷町柏木沢今宮八幡神社を訪ねました。大きな木木に囲まれ、歴史を感じさせて呉れた御社で多くの石神仏が建立祀られて居ました。
古い石宮も祀られて居り、古くからのこの地域の信仰の深さを覗い知る事が出来ました。

お庚申様にしても「1678年(干時4年)に建立祀られて居り、「1760年「宝暦10年」に建立された庚申供養塔、女人講も盛んだった様で、女人講、女人講の主尊、如意輪観音像も並んで建立祀られて居りました。

庚申石宮「1687年『干時4年」の建立

庚申供養塔 「1760年「宝暦「10年」の建立

秋葉大神「1892年「明治25年」の建立
奉賛馬頭観世音「1864年「元治元年」の建立

如意輪観音像「1811年「文化8年」の建立
参考文献 箕郷町石造文化財
古い石宮も祀られて居り、古くからのこの地域の信仰の深さを覗い知る事が出来ました。
お庚申様にしても「1678年(干時4年)に建立祀られて居り、「1760年「宝暦10年」に建立された庚申供養塔、女人講も盛んだった様で、女人講、女人講の主尊、如意輪観音像も並んで建立祀られて居りました。
庚申石宮「1687年『干時4年」の建立
庚申供養塔 「1760年「宝暦「10年」の建立
秋葉大神「1892年「明治25年」の建立

奉賛馬頭観世音「1864年「元治元年」の建立

如意輪観音像「1811年「文化8年」の建立
参考文献 箕郷町石造文化財
2014年07月19日
箕郷町釣り堀センターを訪ねて
現役時代同じ飲食店組合の役員同士で長く懇意だった箕郷町善地駒寄の榛名高原釣り堀センター先代の近況を知ると共に久し振りに釣りを楽しみたくなり、さる7月17日午後訪ねました。
先代は私より3歳年上ですが、お元気で艶も良く、店を手伝ったり、農作業をして居り、今日も午前中農作業をして来たと話されました。お元気な旧友に会えて嬉しい限りでした。

貸し竿を借りて暫く糸を下ろして見ました。静かで木立に囲まれた山間の池ですが水の流れの音、さえずる小鳥の声を聞きながらの久し振りの釣り、マスを釣り上げた時の心躍る喜び、本当に心癒されました。
平日でお客は少なく魚を焼く炭は種火だけでしたが、我儘を云って釣ったマスを焼いて貰いました。

やはりアユやマスは炭火焼が最高です。魚焼きで魚を横にして焼くのと違い、時間を掛けて櫛に刺して立てて焼く魚の味は格別です。
高崎市箕輪小学校から榛名湖へ通ずる道の南側に有る、釣り堀ですが、入口の反対側の休耕田にイノシシが出て来て田圃中を掘り起こして居ると云うので見に行きました。県道の直ぐ傍までイノシシが鼻で掘り起こして居た現場を始めて見ました。

帰りに善地駒寄集会所前に建立祀られて居た。石造文化財を写真に収め帰宅しましたが、命洗えた半日でした。お土産に持ち帰り妻と二人で食べたマスの味は最高でした。

奉造立像庚申供養塔「1692年「元禄5年」の建立

庚申供養塔「1824年「文政7年」の建立
参考文献 箕郷町の石造文化財
先代は私より3歳年上ですが、お元気で艶も良く、店を手伝ったり、農作業をして居り、今日も午前中農作業をして来たと話されました。お元気な旧友に会えて嬉しい限りでした。

貸し竿を借りて暫く糸を下ろして見ました。静かで木立に囲まれた山間の池ですが水の流れの音、さえずる小鳥の声を聞きながらの久し振りの釣り、マスを釣り上げた時の心躍る喜び、本当に心癒されました。
平日でお客は少なく魚を焼く炭は種火だけでしたが、我儘を云って釣ったマスを焼いて貰いました。

やはりアユやマスは炭火焼が最高です。魚焼きで魚を横にして焼くのと違い、時間を掛けて櫛に刺して立てて焼く魚の味は格別です。

高崎市箕輪小学校から榛名湖へ通ずる道の南側に有る、釣り堀ですが、入口の反対側の休耕田にイノシシが出て来て田圃中を掘り起こして居ると云うので見に行きました。県道の直ぐ傍までイノシシが鼻で掘り起こして居た現場を始めて見ました。
帰りに善地駒寄集会所前に建立祀られて居た。石造文化財を写真に収め帰宅しましたが、命洗えた半日でした。お土産に持ち帰り妻と二人で食べたマスの味は最高でした。
奉造立像庚申供養塔「1692年「元禄5年」の建立
庚申供養塔「1824年「文政7年」の建立
参考文献 箕郷町の石造文化財
2014年07月14日
箕郷町法峰寺を訪ねて
高崎市箕郷町法峰寺を訪ねました。法峰寺は箕輪城址南側に有り、山門前には箕輪城で使って居た、大切な水が湧き出して居る処が有り、当時は水曲輪として使用され、現在は蛍峰園として『箕郷町ホタルの会』の皆さんが年間を通じて蛍の育成を行って居り、毎年7月の第一日曜日をほたる祭りと決めて今年はさる7月6日に盛大に行われ、未だ提灯等飾られて有りました。
蛍峰園には、最近イノシシが出没する様で注意書きが張り出されて有りました。
山門前には庚申像が祀られて居り、境内には馬頭尊像など多くの石仏が祀られて居ました。

箕輪小学校前法峰寺参道入り口には、さる7月6日に行われたほたる祭りの看板提灯等未だ飾られて有りました


蛍峰園にはいのしい出没注意の張り紙、ロープも張って園内に入らないように注意して有りました。



法峰寺本堂西側には「1616年「文化13年」建立の馬頭尊像を始め、「1862年「文久元年」建立の馬頭尊像等五体の馬頭尊像が建立祀られて居ました。

箕輪城で大事に使われた湧水の場所を示す看板。

山門前には無縁仏でしょうか、一カ所に集められ、多くの石仏が建立祀られて居ました。
参考文献 箕郷町石造文化財
蛍峰園には、最近イノシシが出没する様で注意書きが張り出されて有りました。
山門前には庚申像が祀られて居り、境内には馬頭尊像など多くの石仏が祀られて居ました。

箕輪小学校前法峰寺参道入り口には、さる7月6日に行われたほたる祭りの看板提灯等未だ飾られて有りました


蛍峰園にはいのしい出没注意の張り紙、ロープも張って園内に入らないように注意して有りました。



法峰寺本堂西側には「1616年「文化13年」建立の馬頭尊像を始め、「1862年「文久元年」建立の馬頭尊像等五体の馬頭尊像が建立祀られて居ました。

箕輪城で大事に使われた湧水の場所を示す看板。

山門前には無縁仏でしょうか、一カ所に集められ、多くの石仏が建立祀られて居ました。
参考文献 箕郷町石造文化財




